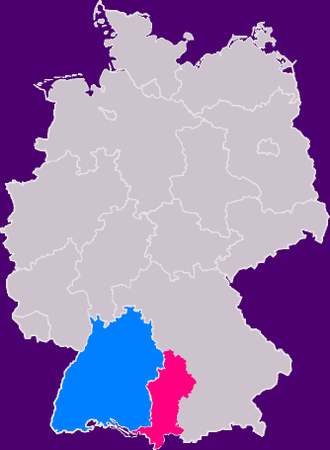.
「奥の細道」の「序」
「月日は百代の過客にして、行きかふ年もまた旅人なり。
舟の上に生涯を浮かべ、馬の口とらへて老を迎ふる者は、日々旅にして、旅をすみかとす。古人も多く旅に死せるあり。
予も、いづれの年よりか、片雲の風にさそはれて、漂泊の思ひやまず、海浜にさすらへ、去年の秋、江上の破屋に蜘の古巣をはらひて、やゝ年も暮れ、春立てる霞の空に、白川の関越えんと、そぞろ神の物につきて心を狂はせ、道祖神の招きにあひて取るもの手につかず、もも引の破をつづり、笠の緒付けかへて、三里に灸据うるより、松島の月まづ心にかかりて、住める方は人に譲り、杉風が別墅に移るに、
草の戸も 住替る代ぞ ひなの家
表八句を庵の柱に懸置。
弥生も末の七日、あけぼのの空朧々として、月は有明けにて光をさまれるものから、富士の峰かすかに見えて、上野・谷中の花の梢、またいつかはと心細し。
むつまじき限りは宵よりつどひて、舟に乗りて送る。
千住といふ所にて舟を上がれば、前途三千里の思ひ(*)胸にふさがりて、幻のちまたに離別の涙をそそぐ。
行く春や 鳥なき魚の 目は涙
これを矢立ての初めとして、行く道なほ進まず。
人々は途中に立ち並びて、後ろ影の見ゆるまではと、見送るなるべし。」
松尾芭蕉は、弟子の曽良と共に、江戸時代の初期に、江戸の深川の庵を出て、隅田川を北上し、千住で舟を降りて、そこから旅立ち、奥州の地を北上し、日本海側の道を南下し、美濃国の大垣に至る行程を歩いたのです。
それは、元禄2年(1689)3月27日(陰暦。現在の暦では5月16日)、46歳の松尾芭蕉の「漂泊の旅」でした。日光街道、奥羽街道陸、北陸道の各地を訪ねています。そして大垣には、8月21日に到着していますから、156日間、476里余ですから、1500km程に及ぶ長旅だったことになります。
父好みの教育者の建てた中学校を勧められて、受験して入学したのです。小学校のクラスで二人だけ、町内の学校でなく、電車通学で通ったのでした。一人は女子で、同じ敷地の中にある女子部に入り、そして自分だったのです。
その12才の春に、国語の授業のほかに、特別科目があり、一週間に1日の講義がありました。高等部の三年生の国語を担当する教師の特講で学んだのです。時代劇の映画を見て、難しい侍や町人の語った日本語を聞き慣れていましたから、違和感を持たずに、教師の朗読する箇所を、素読したのです。何か、大人になった気分がして、得意な思いをしていたのだと思います。
浅草は知っていましたが、文中にある深川や千住は知りませんでした。親しい友人の会社が日本橋にあって、その社屋の五階に、来客用に宿泊用の部屋と台所があって、当時中国にいましたので、帰国すると、そこを使わせていただいたのです。芭蕉が舟で上った隅田川の河畔でした。
.
.
ある時、自転車を借りて、日本橋の界隈を散策したのです。芭蕉記念館などを訪ねたでしょうか。江戸情緒などを感じられませんでしたが、史跡が残されていて、興味深く時を過ごしたのです。
その隅田川の岸に座って、船の上り下りを眺めていると、芭蕉は、捨て切れない「漂泊の思い」を抱いて、未知の地へ旅立って行き、どんな思いで小舟に揺られ、竿の水音を聞いたのだろうかと、タイムスリップしてでしょうか、しばし思いにしたったのです。
俳人の芭蕉には、多くの弟子がいました。歴史で名高い地を訪ねると共に、俳句のお弟子さんたちを訪問し、句会を持ったのです。雨が降ればぬかるむ道を、雨季には増水する川を、険しい山道も、関所も越えながらの旅でした。その旅の紀行文、訪ねた地での出会いや再会、句会での作句、多くの俳句を詠みながらの旅だったのです。
最初の訪問地が、下野国の「煙立つ」と、平安期から詠み継がれた、下野惣社の「室の八島」でした。芭蕉は、次のように書き残しています。
「室の八嶋に詣(けい)す。同行曾良が曰はく、「此の神は、木の花さくや姫の神と申して、富士一体なり。無戸室に入りて焼け給ふ(たもう)ちかひのみ中に、火々出見(ほほでみ)のみこと生まれ給ひしより、室の八嶋と申す。又、煙を読み習はし侍る(はべる)もこの謂はれ(いわれ)なり。」将(はた)、このしろといふ魚を禁ず。縁起の旨、世に伝ふ事も侍りし。」
ここは、「日本書記」にも記されていて、多くの俳人、歌人が詠んでいる地なのです。今春、お隣に住む方にお連れ頂いて、下野国分寺跡と国分尼寺跡で、淡墨桜の観桜をし、下野薬師寺跡、下野国国庁跡などを訪ねたのです。今は下野市や栃木市になっていて、この街々の誇る観光名所であります。
子どもの頃に、家出を二度ほどして、「寂しさ」とか「孤独」などの思いを経験したからでしょうか、自分も「漂泊の思いやまず」で、あちらこちらと旅をさせていただきました。芭蕉は周到な旅備へをして、深川を発っています。信長が「人間五十年」といったのですが、間もなく、その年齢に近い芭蕉は、46歳の年齢で、持病持ちでもあったのです。それでも、旅や再会や出会いを求め、見知らぬ地を訪ねたのです。
李白や杜甫を憧れた文人魂は、「旅に死す」の覚悟で、長距離を走破するのです。昭和の中学生に、感銘を与えるような旅をした人です。自分も、自分に定められた旅の途上にあるように思う今です。昨日も、看護師さんが、『クシャミをしなかった?』と言っていました。医療技師と噂をしたのだそうです。若く見えても、歳は歳で、弱さを覚える年齢ですが、まだまだ生きて、子や孫や友人たちを愛していきたいのです。
(ウイキペディアによる「芭蕉出立」、「室の八島」、「杜甫の草堂」です)
.