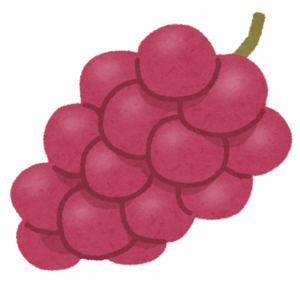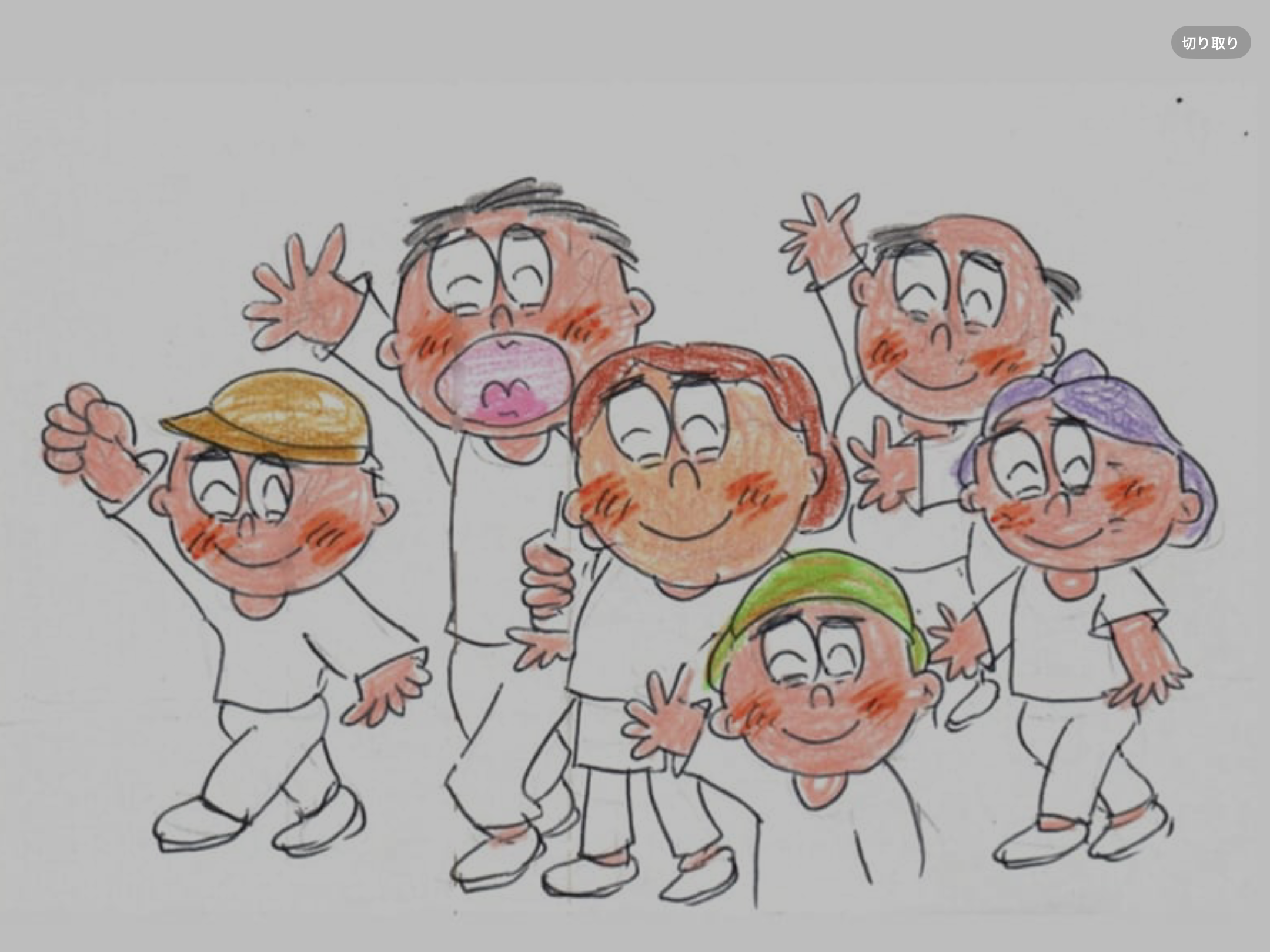『熱いだろうなあ!』と思わされた、あの鉄板の上にのせられた「たい焼き」の様に感じたのでしょうか、何日か前に、この歌が、自分の口から突いて出てしまいました。きっと熱帯のアフリカなどにも比べられないほどの暑さに閉口していたからに違いありません。
華南の街で、スーパーマーケットに行く道を歩いていた時に、小型犬が、道の水溜まりに腹ばいになっていたのを、驚いて見たことがありました。そればかりではなく、道路脇に植えられた街路樹の陰のコンクリートの上で、裸のお腹を出して寝ているおじさんも見掛けたのです。その街は、中国一熱い街だと、地元の人が言っていました。
その街に住み始めたばかりの頃に、大きな川の脇で、丘陵の下にあった棟割長屋は、エアコンなしの家ばかりでした。まだ十何階もある高層アパート群が建てられる前の頃でしたが、入り口の戸も窓も開けっ放しで、熱い夏を過ごしている一郭がありました。何年かして、それが街の景観を良くするためにでしょうか、みんな取り壊されてしまいました。
替え歌にして、エアコンのある部屋で、この歌を歌っていますと、余計暑くなってしまうのです。冷え過ぎますと、古傷が痛むので、当代、「的確なエアコン設定論」の〈28℃の除湿〉、〈普通〉のエアコン設定にしていますが、朝方の散歩でさえも、帰ってくると汗が流れてくるほどなのです。
県北に住むお兄さんが、この街に住む妹さんの家を訪ねて、今更ながら、暑さの酷さを言っておられたのだそうです。前橋や熊谷や佐野などの北関東の街も、今夏の暑い街に数え上げられているのですが、まあ閉口するほど、まだ生かされているほどの暑さなのです。昔住んでいた八王子も、ニュースで報じられる街になっていますので、兄弟たちの住む都下の街も、名こそ挙げられませんが、猛暑の街に違いありません。
この「およげ!たいやきくん」への作詞者のやさしさの溢れる願いの様に、茨城か湘南の海に行って、泳ぎたい気持ちです。台風接近の遊泳禁止の海で、泳ぐほどのバカ者でしたが、憐れみ深い神さまは、送ってくださった波で、サーッと浜に運ばれて、命拾いをしました。海好きの私は、海の驚くほどの猛威を知っているのですから、恐怖と救いの二面を経験したので、最近はなかなか海に近づけません。
この街では、子どもたちが多くいた時代、我々世代のお父さん、お母さんのお話を聞くと、高速道路がなかった時代でしたので、朝早くバスで出かけて、茨城の海に出かけたのだそうです。楽しく賑やかだった思い出話をしてくれました。
大洗の海水浴場へ行ったのでしょうか。元気で、自治会の子供会の夏の行事が、盛んに行われていた時代です。目を細めて、子どもたちのことを思い出して、語っている目が、懐かしさに溢れていました。そう言えば、わが家でも、わざわざ、北茨城の海に出かけたことがありました。海水浴場で聞いた、茨城弁が懐かしく思い出されてきます。
イカの姿焼きやかき氷が美味しかったのですが、もうずいぶん食べていません。鯛焼きだけは、東武百貨店の支店があって、そこで売っていて、時々食べるのです。父二代目のあんこ党なのです。「およげ!たいやきくん」は、あの焼かれたたい焼きを、海で泳がせたくて作詞されたのだと言います。大海原を自由に泳いでいるご自分も重ねていたのでしょうか。
(“いらすとや”の鯛焼き、海水浴のイラストです)
.