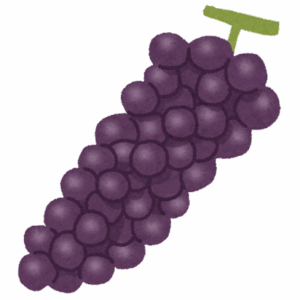.
.
家族で、海水浴に行く途中、ある公園で休んでいたことがありました。そこに歌碑があったのです。千葉県の成東町(現在は山武市成東)の城址にあった公園でした。その歌碑には、「里の秋」の歌詞が刻まれていました。作詞者は、斎藤信夫で、この成東町(現・山武市)の出身だったのです。
この歌は、戦時下に、戦地にいるお父さんの慰労の思いを詠んだ詩でした。一億日本が、その戦争を「聖戦」と定めて、戦勝祈願をして、勝ち戦を願っていたのです。国民学校(小学校)の教員であった斉藤信夫も、そう願って、「星月夜」と言う題で、作詞したのです。一番と二番は同じで、三番と四番は次の様でした。
3 きれいなきれいな椰子の島/しっかり護って下さいと/ああ父さんのご武運を/今夜も一人で祈ります
4 大きく大きくなったなら/兵隊さんだようれしいな/ねえ母さんよ僕だって/必ずお国を護ります
戦意高揚、戦地に赴いた兵隊さんたちの慰労の思いを込めて、戦時色の濃い歌詞だったのです。そんな一億の願いは叶わず、戦争に負けてしまったわけです。そんな戦後に、詞を書き変えて、この歌をレコーディングすると言うことになって、斎藤は「里の秋」と改題し、三番と四番に変わる歌詞を作り直す様に、レコード会社から要請されたのです。
斎藤は、教師として、戦時下、戦勝を願い、日本精神で鼓舞したことに、教師としての戦争責任を感じて、教職を退いていたのです。それで改作した「里の秋」を、NHKから、川田雅子の歌唱で放送しました。この歌が放送されると、驚くほどに強烈な反響を呼んで、小学生ばかりではなく、敗戦に打ちひしがれていた全国民が愛唱する歌の一つとなったのです。
1 静かな静かな 里の秋
お背戸(せど)に木の実の 落ちる夜は
ああ母さんと ただ二人
栗の実煮てます いろりばた
2 明るい明るい 星の空
鳴き鳴き夜鴨(よがも)の 渡る夜は
ああ父さんの あの笑顔
栗の実食べては 思い出す
3 さよならさよなら 椰子(やし)の島
お舟にゆられて 帰られる
ああ父さんよ 御無事でと
今夜も母さんと 祈ります
尾瀬は、夏が来るとですが、秋が来れば思い出すのは、この童謡なのです。有名な観光地ではなく、どこの村にも、どこの町にも、普通にあった日本的な佇まいを思い起こすわけです。
戦時下に生まれたからでしょうか、予科練や海軍兵学校に憧れた、戦後の流れに反した願いを心のうちに温めた自分ですが、割烹着を着た母の、料理していた姿、掃除をしていた振る舞い、買い物籠を下げて買い出しに行っていた背中が思い出されるのです。負けて手にした平和は、何よりも大きな安心でした。
ウクライナやパレスチナでの戦争、東アジアの不穏な動き、旧東欧諸国や中近東諸国に燻り続けるいざこざは、どうなっていくのは、不安材料は尽きません。二度とすまいと掲げた誓いも、薄ボンヤリしてしまっている日本も、そんな中で、どう対応していくのでしょうか。平和の主は、どんな思いでおいででしょうか。
(“いらすとや”の「葡萄」と「くり」です)
.